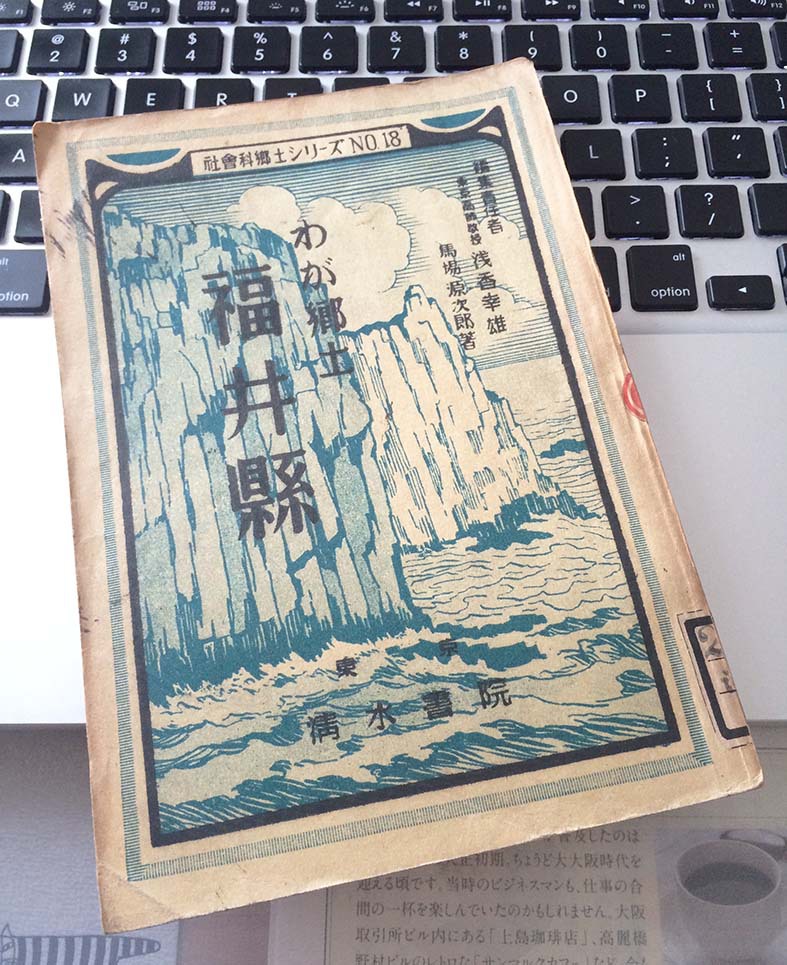
先日、福井県へ行ってきました。福井のある町のとある場所へ行くことがいちばんの目的でした。
その場所は、先日、父方の除籍謄本を取り寄せた時に知った場所、曾祖母の本籍があったところです。
この春、おじを訪ねて昔の話を聞いた時に、「そういえば、ばあさんの家のもともとの出は福井やで」と話してくれました。生まれて数十年、まったく知りませんでした。祖母の生まれについて聞いたことがあったのは、「若いころ北海道にいた」ということ。そんな祖母がなぜ大阪の祖父と出会い、結婚したのか、不思議でした。そこにさらに「福井やで」。ますます祖母がわからなくなりました。おばあちゃん、もっと聞いておけばよかった。
そこで、祖母の戸籍をたどってみました。ちょうど役所が混んでいて、半日間待ち続けて、ようやく手にした除籍謄本。そこにあった曾祖母の結婚前の本籍地の地名。それが福井県のある町でした。まったく知らなかったまちが急に身近になりました。
そのまちは、とてもすてきなまちでした。しかし、曾祖母の家がかつてあった場所は限界集落。数年後には姿を消してしまいます。お宮さんも、すでに合祀された後のようでした。
曾祖母の地を訪ねて、不思議だったことが2つありました。一つ目がそのお宮さんを見た時。朽ち果て始めていて、草も刈られていないそのお社を目にした時、「こんなにぼろぼろになって」と思わず口にしてしまいました。その気持ちは、初めての場所ではなく、自分が見知ったお社と違うという気持ち。そこから出た言葉でした。私にとっては生まれて初めての場所なのに。
そして、もうひとつが曾祖母の本籍地のあたりに行った時、一羽の黒い蝶がどこからともなく飛んできました。静かにそれはやってきて、わたしたちの頭上を飛び、ゆっくりと対岸の森へ消えていきました。
黒い蝶は先祖が姿を変えたものだという話があるそうです。曾祖母は結婚して、この地を出て、遠く北海道へ渡りました。そこで祖母たち兄弟を育てたのでしょう。結婚後、この地へ帰ることはあったのでしょうか。この黒い蝶が、曾祖母の化身のように思えてなりませんでした。

「野間清六」。江南良三の「続・近江商人列伝」で見つけた名前です。
なんだか聞いたことがあるなと思い、調べてみると、日本の美術史に力を尽くし、名を残した方でした。東京国立博物館の館長としても活躍をされていたそうです。
そしてこの「野間清六」という名は、近江商人の名としても足跡を残しています。
江戸中期(延享年代:1744ー)、下総の結城に店を開いたとされています。醸造業を営み、「角大」近江屋久右衛門と称し(※1)、江戸末期には結城の御三家と呼ばれるほどに力をつけ、近江屋は結城藩の御用金を担当、苗字帯刀を許されるまでになります。
明治期、当主だった清六は、書画を愛好し玄人はだしであり、商売への興味が薄れ、明治23年には店を廃業します。その後は、小西吉太郎(金田村浅小井)が継承したそうで、日清戦争の頃に人気を博したといいう「日本誉」というお酒は、この小西が店を引き継いでいた頃の話でしょうか
この後の、清六氏が国立博物館の館長として、日本の芸術に貢献された方です。
そして、この野間家の屋敷は、近江八幡に現存し、本家はNPOの事務局として、分家はボーダレスアートのミュージアムとして用いられているそうです。野間家は、アートとの縁が深いようですね。
【調査事項】
・日本誉とはどんなお酒だったのか:群馬県太田市の山崎酒造が同名のお酒を作っているが、関係があるのか
・結城酒造と野間清六の関係:近江屋久右衛門との関係があるとのこと、これは野間家の祖か。
【註】
※1 江南「続・近江商人列伝」では「大角」と記されています(50p)
【参考文献】
江南良三(1990)「続・近江商人列伝」、サンライズ印刷



