
先日、「エジプトに行ってたんや」と祖母が話した曽祖父の弟の話 を書きました。
この度、国会図書館に行く用事があって、そちらで日本綿花さんの社史を見ることができました。
「日本綿花株式会社五十年史」(社史で見る日本経済史 第67巻、ゆまに書房)
そこで曽祖父の弟(曾祖叔父というそうです)の名前を確認。やはり仕事でエジプトに行っていたようです(大正6年にエジプトへ)。
しかもその後は、ヨーロッパへ。
あの時代に、世界を駆け回るだなんて、どんな思いで日々を過ごしていたのでしょうか。
紳士録の記録を追うと、昭和5年には日本に戻ってきていたようです(もう一人の曾祖叔父のもとに寄寓)。
エジプト行きから計算すると13年間、ずっと海外へ渡ったままだったのでしょうか。
「エジプトのおじさん」には息子さんがおられたと叔父から聞いていますが、今は縁がなくなっています。いつか子孫の方にお会いして、お話を聞いてみたいものです。

タイトルの「あきない人びと」の「あきない」とは、
「商い」と「飽きない」とをかけています。
ちょこちょこ書いていますが、私の先祖は、
ちょこちょこ書いていますが、私の先祖は、
大阪の靱で江戸から明治、大正期にかけて商売をしていました。
鰹節問屋ということでしたが、
鰹節問屋ということでしたが、
残念なことに詳しい情報はほとんど子孫のもとには残っていません。
先祖のことを少しでも知りたいと様々な資料を調べていくと、
先祖のことを少しでも知りたいと様々な資料を調べていくと、
当時の商人たちの姿を感じることができるようになってきました。
明治維新、産業の成長、恐慌、戦争、震災と時代の変遷の中生き抜いた商人たち。
時代の荒波を逞しく強かに生きた商人がいました。
明治維新、産業の成長、恐慌、戦争、震災と時代の変遷の中生き抜いた商人たち。
時代の荒波を逞しく強かに生きた商人がいました。
立身出世を遂げた人もあり、紆余曲折を経た人もあり、夢破れた人もいました。
ただ、自らの儲けだけを追求するのではなく、
世の中への貢献を考えた姿も見えるようになってきました。
ただ、自らの儲けだけを追求するのではなく、
世の中への貢献を考えた姿も見えるようになってきました。
彼らの生き様には、眼を見張るものがありました。
良い時もあれば悪い時もある。
頂点も底も経験する。
頂点も底も経験する。
酸いも甘いも知っている。
彼らを知れば知るほど、「飽きない人」と感じます。
彼らは、「商い人」でありながら、「飽きない人」でした。
そんな商人たちのことを調べているうちに、
参考にした本や調べた情報を
他の興味ある方も見られるように整理しようと思うようになりました。
彼らを知れば知るほど、「飽きない人」と感じます。
彼らは、「商い人」でありながら、「飽きない人」でした。
そんな商人たちのことを調べているうちに、
参考にした本や調べた情報を
他の興味ある方も見られるように整理しようと思うようになりました。
ここを通じて、近代の商人に関心ある人とも交流できればとも思っています。

祖母が生前、写真を見せてくれました。
たくさんのセピア色の写真。私にとっての曽祖父が孫(叔父)を抱いてうつっていたり。祖父の丁稚時代の前掛け姿も。初めて見るものばかりで興味津々。
その時、祖母が
「この人はエジプトに行ってたんや」
と。
どんな写真を見て祖母がそう言ったのか思い出せないのですが、「この人」というくらいだから、誰かの写真を指していたのだと思います。顔がうつっていたのでしょうか、まったく思い出せません。
祖母の言う「この人」とは曽祖父の弟にあたる人の話でした。
「エジプトって、エジプト?」
私が問うと、
「そうや」
「エジプトってピラミッドあるところやで?」
「うん、そうや」
写真の年代は戦前のものばかり。しかも曽祖父の弟ですので、明治生まれの人です。その頃にエジプトに行く人ってどんな人?
何者なんだろう???
あれからもう20年近く。
ようやく手がかりを見つけました。
近代デジタルライブラリーのおかげです。
曽祖父には弟達がいたのですが、そのうちの一人の名前を調べていくと、かつての日本綿花に勤めていたらしいことがわかりました。
日本綿花は今の双日。戦前の専門商社です。その日本綿花がエジプトと取引をしていました。エジプトは綿花の大産地です。
曽祖父の弟は、仕事の関係でエジプトに行っていたのかもしれません。
双日は、会社の歴史について丁寧にまとめている企業でした。会社に問い合わせれば、何かわかるかもしれませんね。
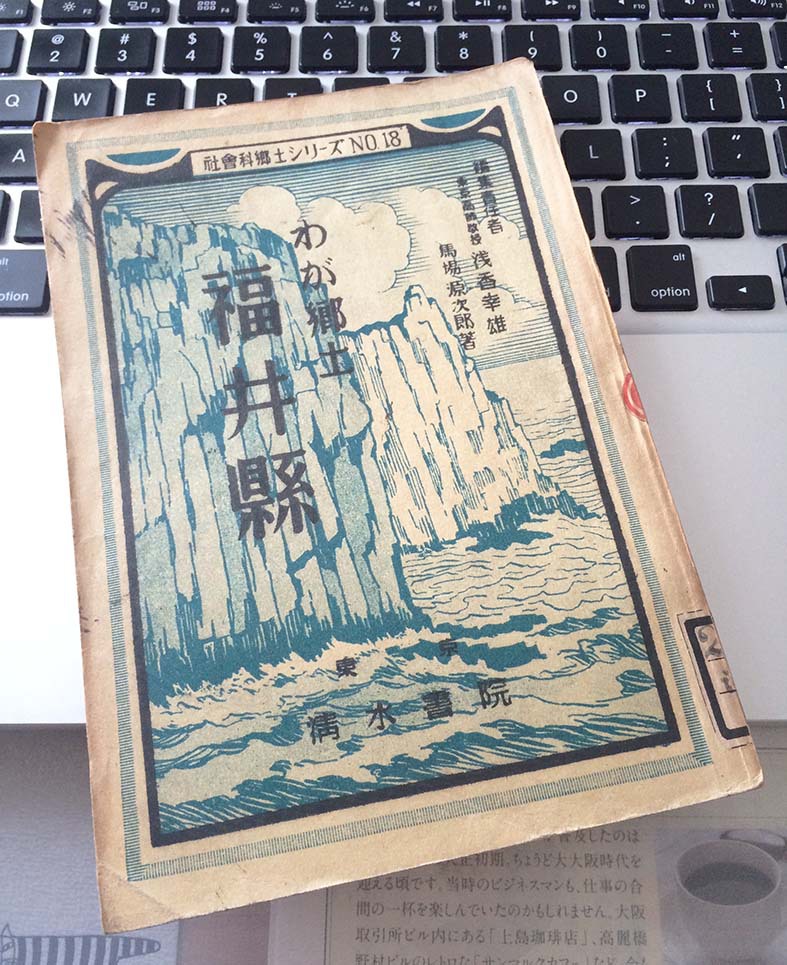
先日のっけた画像の本ですが、見ての通り、かなり古めです。香ばしい香りがします。
祖母のルーツだという福井県について調べるために、県立図書館で借りてきました。
著者は馬場源次郎。編集責任者は浅香幸雄(東京高師教授)。浅香幸雄さんは有名な地理歴史学者とのこと、馬場さんについては情報が見つけられませんでした。
「刊行のことば」によると、「各縣一流の社會科の先生」とのことなので、馬場さんもおそらく福井県の社会科の先生なのでしょう。
今から約70年前の本です。戦後の新しい時代を作る世代に向けて、意欲的に書かれた本のように感じられました。
【情報】
馬場源次郎(編集責任者 浅香幸雄)
「社會科郷土シリーズNO.18 わが郷土福井縣」
1949(昭和24)年
清水書院
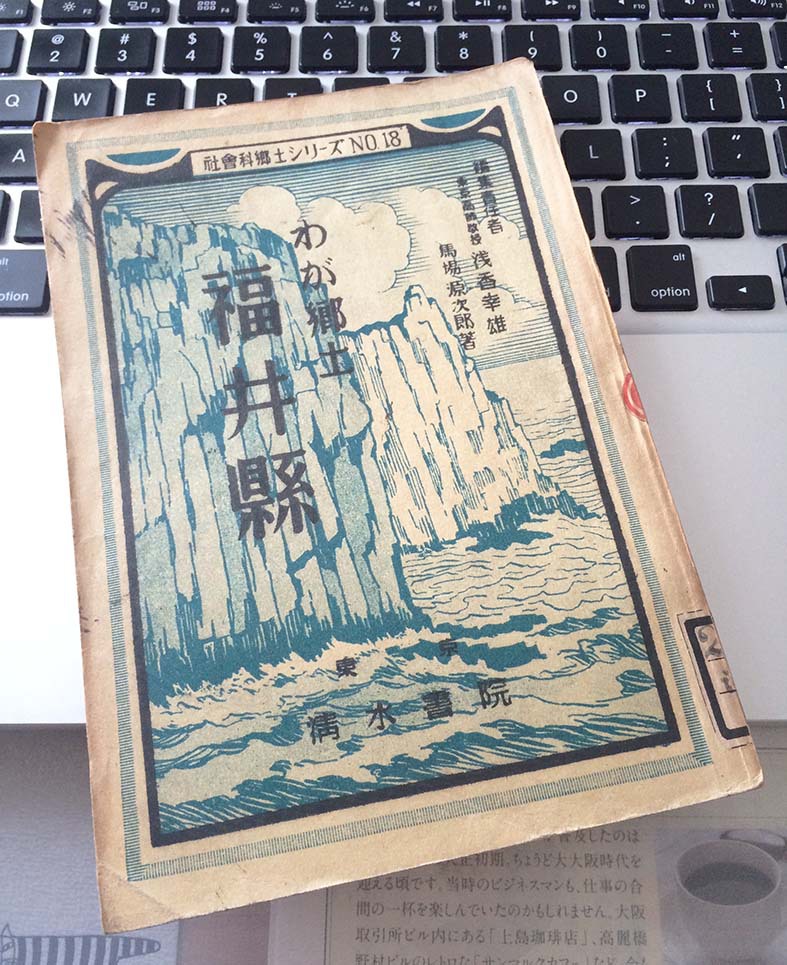
先日、福井県へ行ってきました。福井のある町のとある場所へ行くことがいちばんの目的でした。
その場所は、先日、父方の除籍謄本を取り寄せた時に知った場所、曾祖母の本籍があったところです。
この春、おじを訪ねて昔の話を聞いた時に、「そういえば、ばあさんの家のもともとの出は福井やで」と話してくれました。生まれて数十年、まったく知りませんでした。祖母の生まれについて聞いたことがあったのは、「若いころ北海道にいた」ということ。そんな祖母がなぜ大阪の祖父と出会い、結婚したのか、不思議でした。そこにさらに「福井やで」。ますます祖母がわからなくなりました。おばあちゃん、もっと聞いておけばよかった。
そこで、祖母の戸籍をたどってみました。ちょうど役所が混んでいて、半日間待ち続けて、ようやく手にした除籍謄本。そこにあった曾祖母の結婚前の本籍地の地名。それが福井県のある町でした。まったく知らなかったまちが急に身近になりました。
そのまちは、とてもすてきなまちでした。しかし、曾祖母の家がかつてあった場所は限界集落。数年後には姿を消してしまいます。お宮さんも、すでに合祀された後のようでした。
曾祖母の地を訪ねて、不思議だったことが2つありました。一つ目がそのお宮さんを見た時。朽ち果て始めていて、草も刈られていないそのお社を目にした時、「こんなにぼろぼろになって」と思わず口にしてしまいました。その気持ちは、初めての場所ではなく、自分が見知ったお社と違うという気持ち。そこから出た言葉でした。私にとっては生まれて初めての場所なのに。
そして、もうひとつが曾祖母の本籍地のあたりに行った時、一羽の黒い蝶がどこからともなく飛んできました。静かにそれはやってきて、わたしたちの頭上を飛び、ゆっくりと対岸の森へ消えていきました。
黒い蝶は先祖が姿を変えたものだという話があるそうです。曾祖母は結婚して、この地を出て、遠く北海道へ渡りました。そこで祖母たち兄弟を育てたのでしょう。結婚後、この地へ帰ることはあったのでしょうか。この黒い蝶が、曾祖母の化身のように思えてなりませんでした。

「野間清六」。江南良三の「続・近江商人列伝」で見つけた名前です。
なんだか聞いたことがあるなと思い、調べてみると、日本の美術史に力を尽くし、名を残した方でした。東京国立博物館の館長としても活躍をされていたそうです。
そしてこの「野間清六」という名は、近江商人の名としても足跡を残しています。
江戸中期(延享年代:1744ー)、下総の結城に店を開いたとされています。醸造業を営み、「角大」近江屋久右衛門と称し(※1)、江戸末期には結城の御三家と呼ばれるほどに力をつけ、近江屋は結城藩の御用金を担当、苗字帯刀を許されるまでになります。
明治期、当主だった清六は、書画を愛好し玄人はだしであり、商売への興味が薄れ、明治23年には店を廃業します。その後は、小西吉太郎(金田村浅小井)が継承したそうで、日清戦争の頃に人気を博したといいう「日本誉」というお酒は、この小西が店を引き継いでいた頃の話でしょうか
この後の、清六氏が国立博物館の館長として、日本の芸術に貢献された方です。
そして、この野間家の屋敷は、近江八幡に現存し、本家はNPOの事務局として、分家はボーダレスアートのミュージアムとして用いられているそうです。野間家は、アートとの縁が深いようですね。
【調査事項】
・日本誉とはどんなお酒だったのか:群馬県太田市の山崎酒造が同名のお酒を作っているが、関係があるのか
・結城酒造と野間清六の関係:近江屋久右衛門との関係があるとのこと、これは野間家の祖か。
【註】
※1 江南「続・近江商人列伝」では「大角」と記されています(50p)
【参考文献】
江南良三(1990)「続・近江商人列伝」、サンライズ印刷



